不動産の保有時における税金【住宅借入金特別控除 住宅ローン控除】
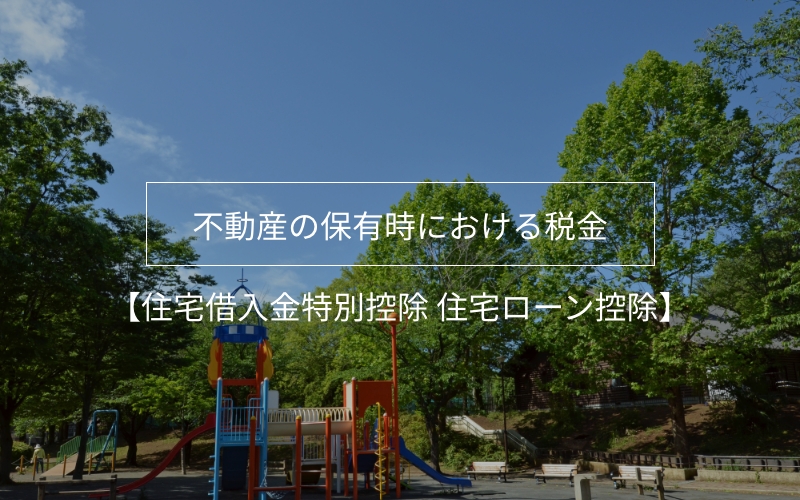
1.住宅ローン控除とは
2.住宅ローン控除の要件
住宅ローン控除の適用を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
【適用を受ける人の要件】
合計所得金額が3,000万円以下の年に限られ、入居した年以前3年間、以後2年間内に次の特例を受けていないこと。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 居住用財産の長期譲渡所得の軽減税率の特例
- 中高層耐火建築物等の建築のための特例
【住宅ローンの要件】
借入期間が10年以上の、次に掲げる借入金等が控除の対象とされる住宅借入金等に該当します。
- 住宅の取得や家屋の増改築(以下「住宅の取得等」といいます)に要する資金に充てるために、民間の金融機関、地方公共団体、住宅金融専門会社、または各共済組合などから借り入れた借入金(当該住宅の敷地に対する一定の借入金も含みます)
- 建設業者に対するs工事の請負代金に係る債務
- 宅地建物取引業者、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社等の居住用家屋の分譲者に対するその住宅の取得等(当該住宅の敷地に対する一定のものも含みます)の対価に係る債務
- 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社または日本勤労者住宅協会からの中古住宅の取得(当該中古住宅の敷地である一定の土地等の取得も含みます)に係るこれらの法人に対する債務
- 住宅の取得等に要する資金に充てるために、その者に係る使用者から借り入れた借入金(当該住宅の敷地である一定の土地等の取得に要する借入金も含む)、または、その者に係る使用者に対する住宅の取得等(当該住宅の敷地である一定の土地等の取得も含みます)の対価に係る債務
なお、上記に該当する借入金や債務であっても、次に掲げるものは対象から除外されます。
- 利息に対応する借入金または債務
- 会社役員がその会社から借り入れた前記ホの借入金
- 無利息または年0.2%未満の利率で借り入れた前記ホの借入金
年利0.2%未満の社内融資や、会社からの利子補給で実質0.2%に満たない利息しか負担していない場合には民間の住宅ローンであっても控除の対象となりません。ただし、公的融資や民間住宅ローンなどの場合で、会社からの利子補給を受けておらず、もともとのローン金利が0.2%未満の借入金は、控除の対象となります。
【住宅等の要件】
控除の対象とされる住宅は次の通りです。
新築住宅
個人が自己の居住の用に供する次に掲げる要件のいずれかを満たす「家屋」(床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその居住の用に供されるものに限ります)
- 1棟の家屋、マンション等で床面積が50m²以上であるもの
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」「都市の低炭素化の促進に関する法律」に規定する一定の家屋
既存住宅
個人が自己の居住の用に供する次に掲げる要件を満たす「建築後使用されたことのある家屋」(床面積の2分の1以上に相当する部分が専らその居住の用に供されるものに限ります)
新築住宅の条件のほか、下記の条件を満たすこと。
- マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの
- 耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたもの
- 上記のいずれにも該当しない建物の場合には、一定の耐震基準(※)に適合するものであること
※ 一定の耐震基準に適合するものとは、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるものに適合する家屋で、その家屋の取得の日前2年以内に耐震基準適合証明書による証明のための家屋の調査が終了したものまたはその家屋の取得の日前2年以内に住宅性能評価書により耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3であると評価されたものをいいます。 また、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものについても軽減措置があります。
家屋の増改築等
個人がその所有している自己の居住用家屋につき行う増築、改築等の工事のうち、次に掲げる要件のすべてを満たすもの。
- その工事に要した費用の額が100万円を超えること
- その工事に係る部分のうちに居住用以外の部分がある場合には、その居住用部分に係る工事に要した費用の額が全体の工事に要した費用の額の2分の1以上であること
- その工事をした後の家屋の床面積が50m²以上であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること
- その工事をした後の家屋が、主として居住の用に供すると認められるものであること
3.控除が受けられる期間
4.控除額の計算
【控除の対象となる借入金】
平成26年4月から平成33年12月までの入居で消費税率8%または10%が適用される場合は4,000万円までが対象となります。 なお、消費税率が8%または10%でない場合は2,000万円までが対象です。
【住宅ローン控除額】
原則
| 居住年 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額(10年分合計) |
|---|---|---|---|---|
| 特定取得以外 | 2,000万円 | 10年間 | 1.0% | 200万円 |
| 特定取得(平成26年4月~令和2年12月)(※) | 4,000万円 | 400万円 |
認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合
取得した住宅が認定長期優良住宅または認定低炭素住宅に該当する場合には、以下の表のように控除額が増額されます。この特例は新築のみに適用されます。
| 居住年 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額(10年分合計) |
|---|---|---|---|---|
| 特定取得以外 | 3,000万円 | 10年間 | 1.0% | 300万円 |
| 特定取得(平成26年4月~令和2年12月)(※) | 5,000万円 | 500万円 |
※取得した住宅に係る消費税率が8%または10%の場合、入居日が平成26年4月以後であっても、免税事業者からの取得で消費税等がかからない場合は、特定取得以外の限度額が適用されます。
【住民税における住宅ローン控除制度】
住宅ローン控除額を所得税額から控除しきれない人については、その控除しきれない額を、住民税から控除することができます
| 居住年 | 控除限度額 |
|---|---|
| 特定取得以外 | 所得税の課税総所得金額×5% (最高 97,500円) |
| 特定取得(平成26年4月~令和2年12月)(※) | 所得税の課税総所得金額×7% (最高 136,500円) |
5.申告手続き
住宅ローン控除の適用を受けるためには、住所地を管轄する税務署に確定申告する必要があります。 給与所得者についてはその後の年分からは会社の年末調整で控除が受けられます。
本コラムは平成30年4月1日現在の法令に基づいて作成されたものであり、現況とは異なる場合があります。
